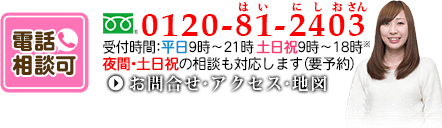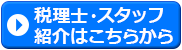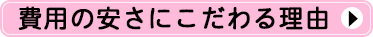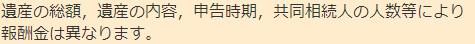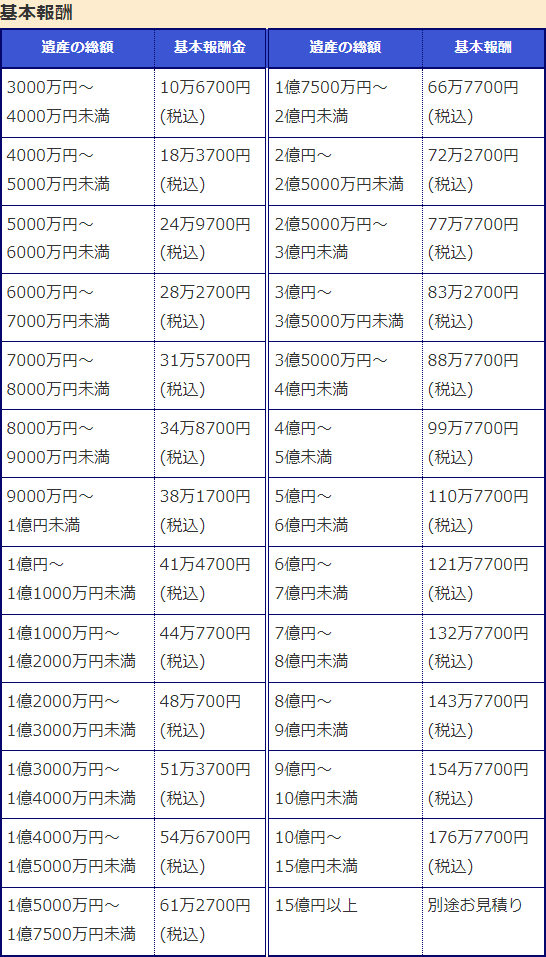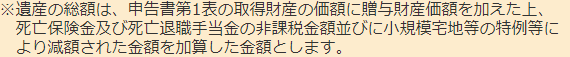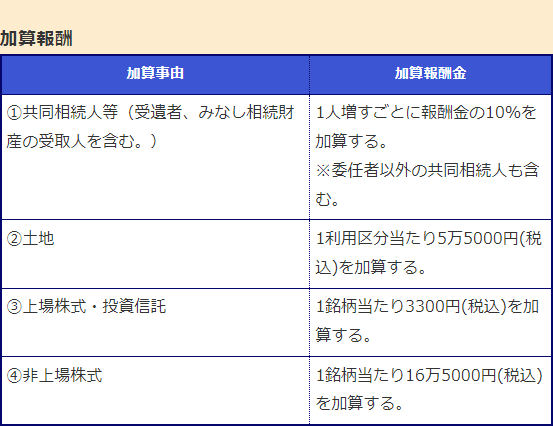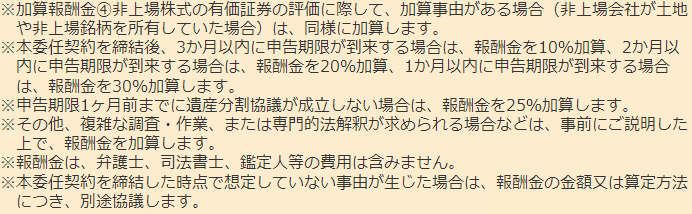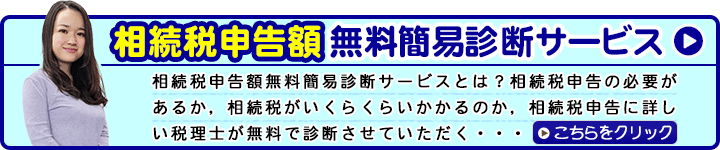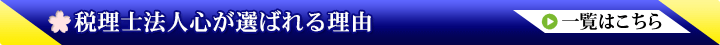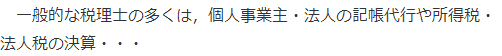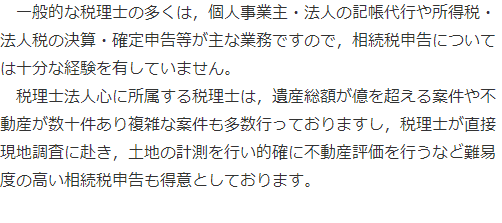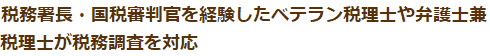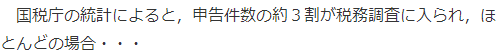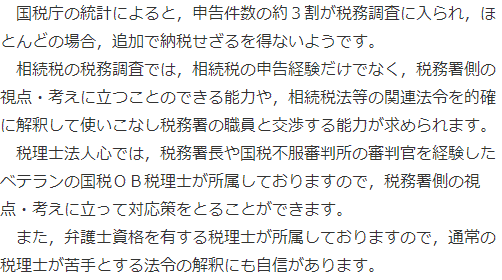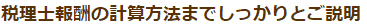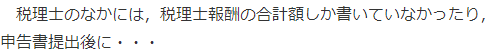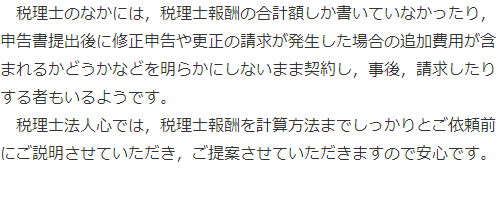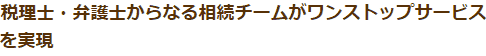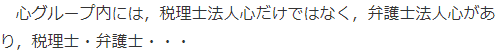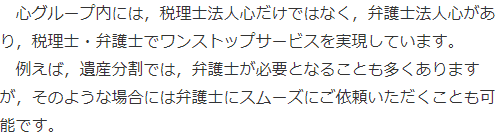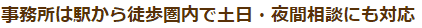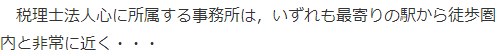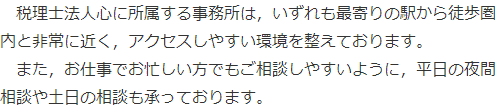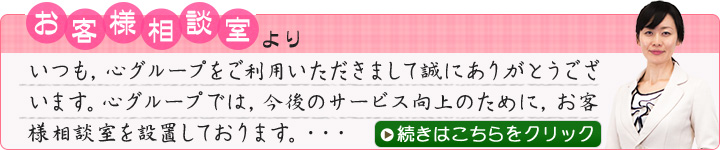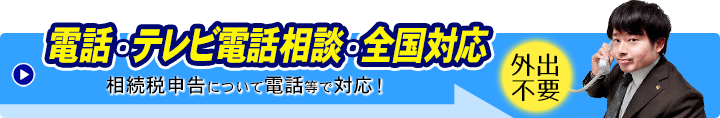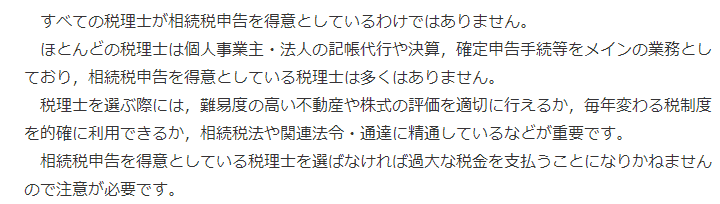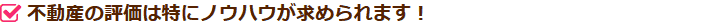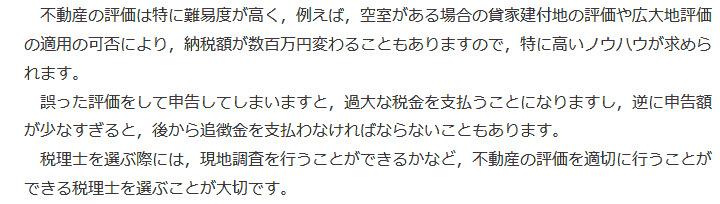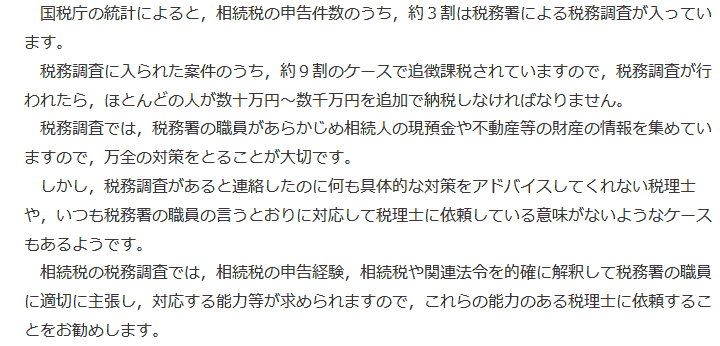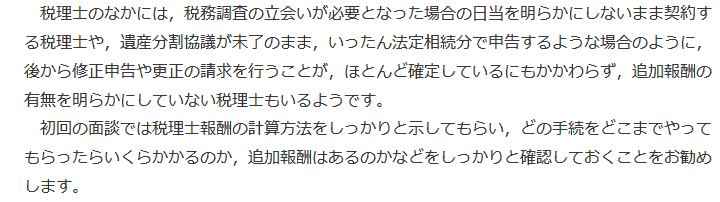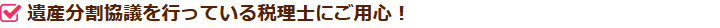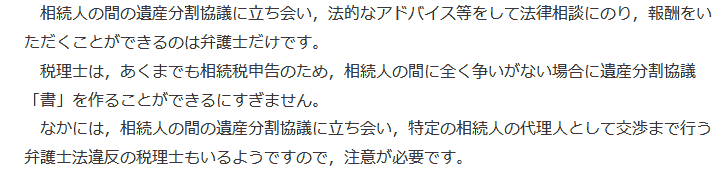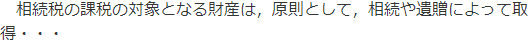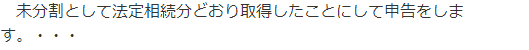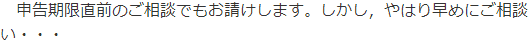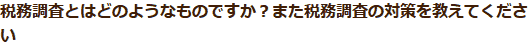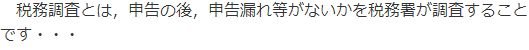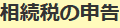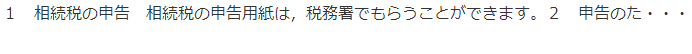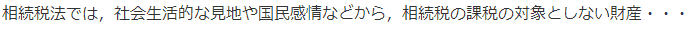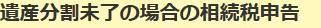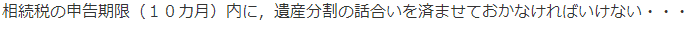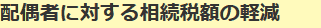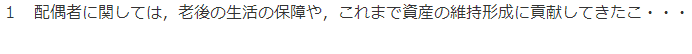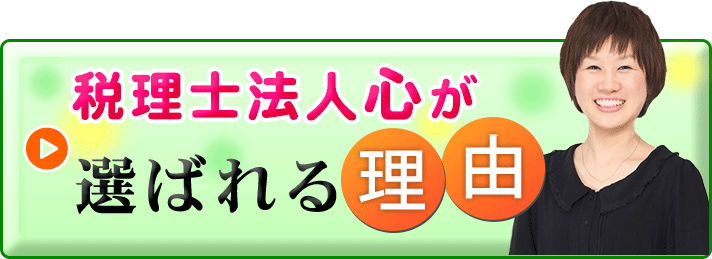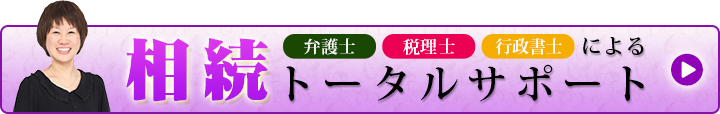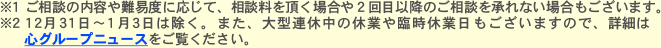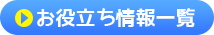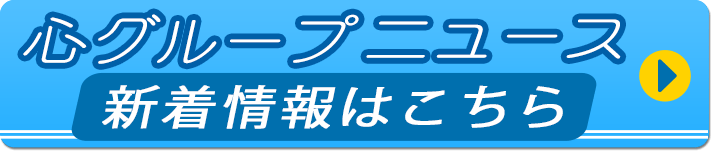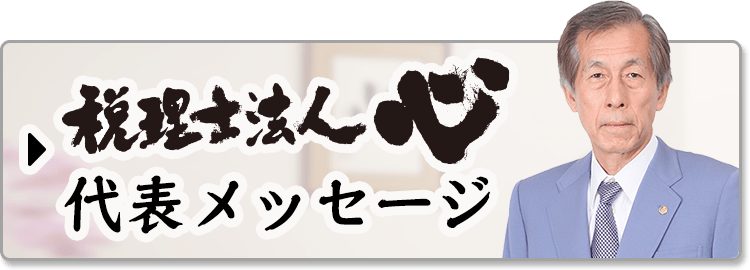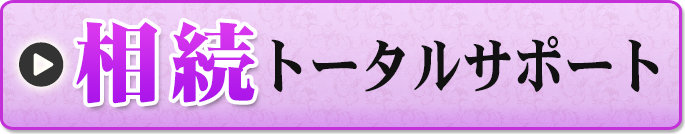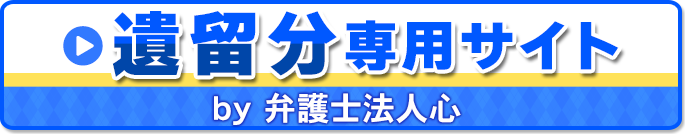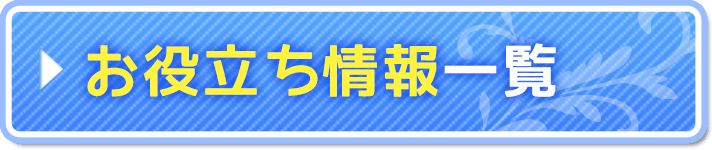相続税について税理士に相談した方がよいケース
1 亡くなる前の場合は基礎控除額を超えているときに要相談

相続税は、基礎控除額を超えている場合に申告・納税が必要となります。
相続税の基礎控除額は、3000万円+(600万円×法定相続人の人数)によって算出されます。
遺産が、この基礎控除額を下回っている場合は、そもそも相続税の申告・納税は必要ありませんので、まずはこの点を確認すべきです。
生前から相続税のシミュレーションを行っておくと、節税対策や納税資金の準備などを検討できるため、おすすめです。
2 亡くなった後の場合はとりあえずまず相談
相続税の申告・納付期限は、亡くなった日の翌日から10か月しかありません。
申告書を作成するためには、収集しなければならない資料もたくさんありますので、まずは、税理士に相談し、相続税申告が必要か、必要であればどのような資料を集めなければならないか、それにはどの程度の時間がかかるかなどを相談し、確認すべきです。
3 相続財産に不動産が含まれる場合も税理士に要相談
不動産のなかでも、土地が相続財産に含まれる場合には注意が必要です。
土地は、固定資産税評価額と相続税評価額が乖離していることが多いからです。
相続税評価額では、「時価」が用いられることになっていますが、固定資産税評価額は時価よりも安く設定されていることが多く、相続人が想定しているよりも相続財産額が大きくなることがあります。
特に、土地のなかに農地や雑種地が含まれている場合は、倍率地域といい、固定資産税評価額の数倍から数十倍の評価額と算定されることもあります。
4 なにが相続財産に含まれるのかわからない場合も要相談
相続財産には、預貯金や不動産だけでなく、生命保険金や死亡退職金なども含まれます。
例えば、生命保険金は、被保険者が被相続人、受取人が相続人、契約者が被相続人の場合、本来であれば受取人である相続人の権利であり、相続財産にはなりません。
また、死亡退職金も受取人が遺族の場合は、遺族の権利であり、相続財産にはなりません。
ただ、これらの権利は、相続税の金額を計算する際には、相続財産とみなして計算することとなっています。
このように、本来であれば相続財産ではないものも、相続税を計算する際には相続財産とみなして計算することがありますので、わからない場合には税理士に相談しましょう。